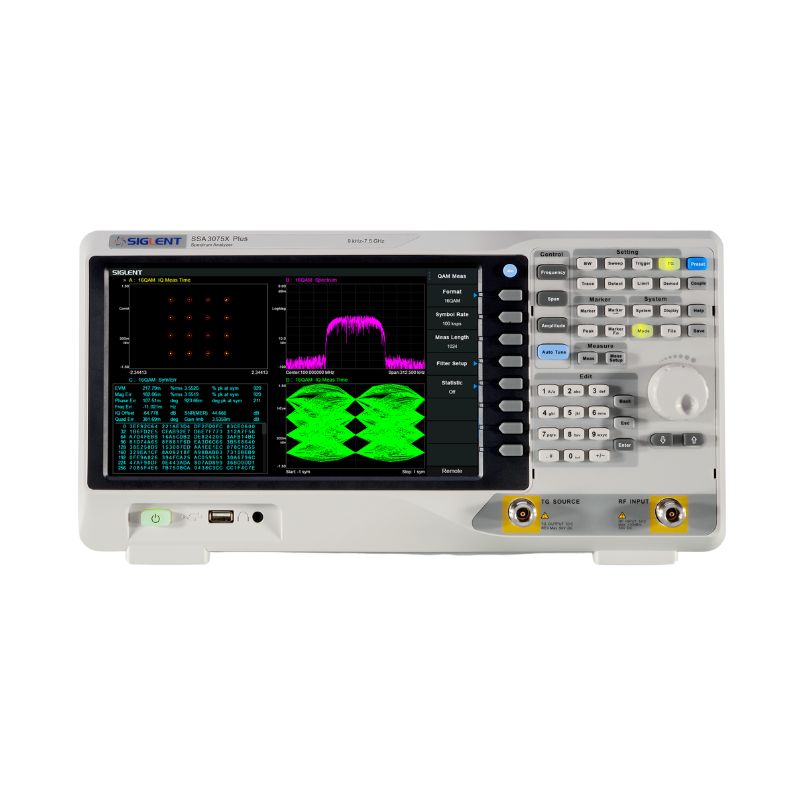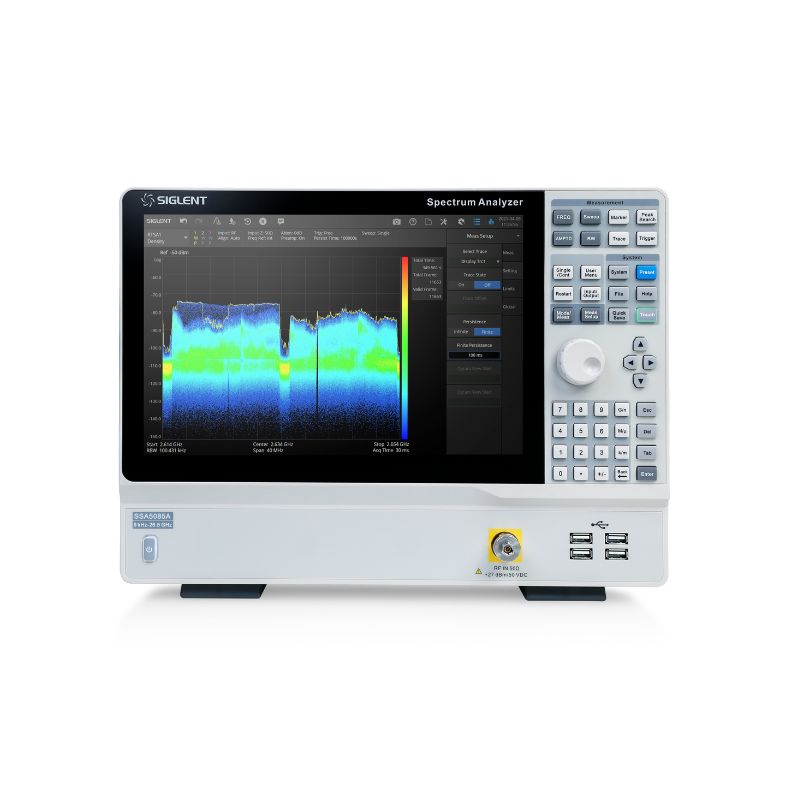ETCは、Electronic Toll Collection Systemの略で、有料道路の料金所をノンストップで通過できる自動料金収受システムのことです。車両に搭載された車載器と料金所の路側アンテナが無線通信し、車両情報を認識して料金を自動的に精算します。
ETCの周波数
ETCの通信には、5.8GHz帯の電波が使われています。
この周波数帯は、DSRC(Dedicated Short Range Communication)と呼ばれる狭域通信の技術を利用しており、ETC以外にも、渋滞情報などを提供するETC2.0の路側機や、一部の交通管制システムにも使われています。
具体的には、送信周波数(路側機から車載器へ)が5.795GHzと5.805GHz、受信周波数(車載器から路側機へ)が5.835GHzと5.845GHzとなっています。これらの周波数が、車載器と路側機の間で料金情報や車両情報などを安全かつ迅速にやりとりするために利用されています。
スプリアス規制とは
スプリアスとは、無線設備から発射される電波のうち、本来の通信に必要な周波数帯から外れて発射される不要な電波のことを指します。この不要な電波は、他の無線機器に干渉して通信障害を引き起こす可能性があるため、電波法によってその強度が厳しく規制されています。この規制がスプリアス規制です。
2005年(平成17年)にこの規制が改正され、より厳しい「新スプリアス規格」が導入されました。この規格に適合しない旧規格の無線機器は、原則として使用が制限されています。これにより、より良好な電波環境を維持・向上させることを目的としています。
「スプリアス」とは、無線設備から発射される電波のうち、本来の通信に必要な周波数帯域の外側に漏れる不要な電波のことを指します。この不要な電波が他の通信に悪影響を与える可能性があるため、電波法でその強さが規制されています。
総務省は、国際的な取り決めに従って、このスプリアスの許容値を厳しくする新しい基準(新スプリアス規格)を設けました。これに伴い、古い基準(旧スプリアス規格)で製造された一部の無線設備が、将来的に使用できなくなる可能性があります。ETC車載器も無線設備の一種であるため、この規制の対象となります。
いつから使えなくなる?
当初は、旧スプリアス規格のETC車載器は「2022年12月1日以降」は使用できなくなるとされていました。しかし、新型コロナウイルスの影響など社会経済情勢への配慮から、新スプリアス規格への移行期限は「当分の間」に延長されています。
そのため、現時点(2025年8月)では、旧スプリアス規格のETC車載器でも引き続き使用することが可能です。
ただし、「当分の間」がいつまでかは明確にされていません。将来的に移行期限が設定され、旧規格のETC車載器が使用できなくなる可能性はあります。
どの機種が対象になる?
主に平成19年(2007年)以前に製造された、旧スプリアス規格で認証を受けたETC車載器が対象となります。
ご自身のETC車載器が対象機種かどうかは、以下の方法で確認できます。
-
車載器メーカーや自動車メーカーのウェブサイトで確認する:メーカー各社が、対象機種の一覧を公開している場合があります。
-
「車載器管理番号」で確認する:セットアップ申込書や証明書に記載されている「車載器管理番号」の最初の数字が「0」から始まるものが旧規格である可能性があります。ただし、メーカーによって異なる場合もあるため、メーカーの情報を確認するのが最も確実です。
2030年問題との違い
ETC車載器には、スプリアス規制の他にも「2030年問題」と呼ばれる別の問題も存在します。
こちらは、ETCシステムのセキュリティ規格が変更されることにより、新セキュリティ規格に対応していない旧型のETC車載器が利用できなくなるというものです。
スプリアス規制の対象機種はごく一部ですが、2030年問題の対象機種はより広範囲にわたると言われています。