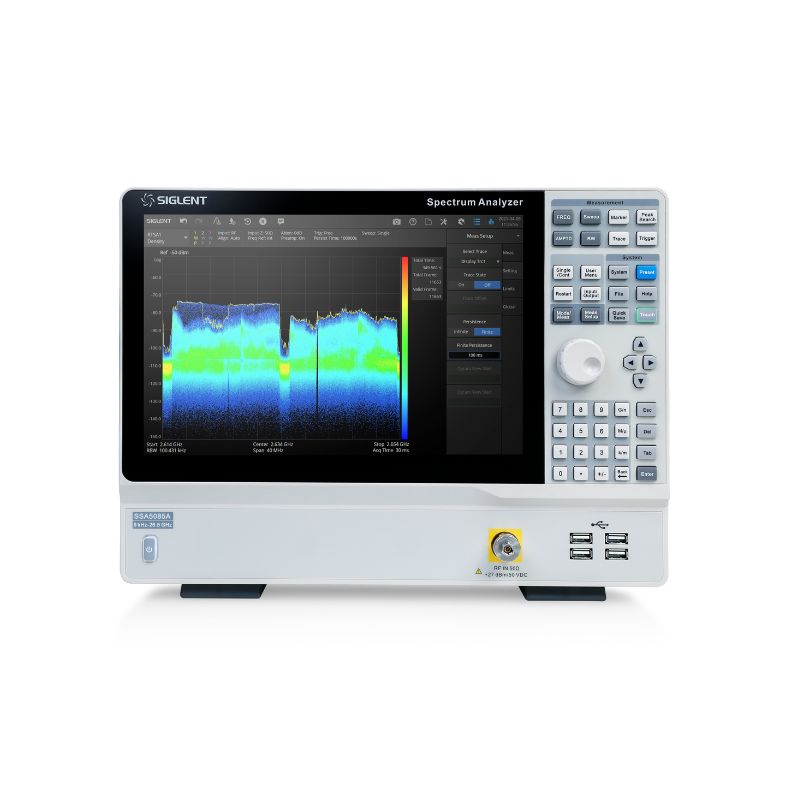D2C(Direct to Cell)衛星とは、通常のスマートフォンなどの地上端末と衛星が直接通信することを可能にする機能を持った衛星のことです。
従来の衛星通信では、専用の大型アンテナや端末が必要でしたが、D2C衛星は、端末側で特別なハードウェアやアプリの変更を必要とせず、既存のLTEなどの標準的な携帯電話規格を利用して直接接続できるように設計されています。
仕組み
D2C衛星は、宇宙空間に存在する「携帯電話タワー」のような役割を果たします。
-
衛星の機能: D2C機能を搭載した低軌道周回衛星(LEO衛星)には、高度なeNodeBモデム(地上の携帯電話基地局の主要な機能を持つ機器)が搭載されています。
-
直接通信: この衛星が、地上の携帯電話ネットワークが届かない圏外エリアにあるスマートフォンと直接通信します。
-
連携: 通信事業者の既存の周波数帯を活用することで、スマートフォンは衛星を通常のローミングパートナーのように認識し、圏外から自動的に衛星接続に切り替わります。
-
データ伝送: 衛星は、レーザーバックホールなどを介して地上のゲートウェイ局や他のStarlink衛星コンステレーションに接続し、データをやり取りします。
主な目的とメリット
D2C衛星の最大の目的は、地球上のモバイル通信圏外をゼロにすることです。
| メリット | 詳細 |
| 通信エリアの拡大(圏外ゼロ) | 山間部、島しょ部、海上など、地上の基地局ではカバーできないリモート地域でも通信が可能になります。 |
| 災害対策 | 地上の通信インフラが被害を受けた際でも、衛星経由で生命を救う重要な接続性(緊急通報、安否確認など)を確保できます。 |
| 既存端末の利用 | 専用機器が不要で、手持ちのスマートフォンをそのまま利用できます。 |
課題(デメリット・制約)
サービス提供の初期段階や技術的な制約として、以下の点が挙げられます。
-
通信速度と遅延(レイテンシ): 地上の5Gネットワークと比べると、現時点では平均スループットが低く(推定約4 Mbpsなど)、遅延も高い傾向があります。
-
屋内浸透性の限定性: D2Cは主に空が見える屋外での利用を想定しており、屋内や地下での通信は難しい場合があります。
-
衛星数の確保: 途切れのない安定した通信を提供するためには、非常に多くのD2C対応衛星を軌道上に配置する必要があります。
-
スマートフォンの電力消費: 衛星と直接通信するため、スマートフォンの電力消費が増加する可能性があります。
下記資料では、au Starlink Directを例にD2Cを詳しく紹介しています。
藤岡雅宣の「モバイル技術百景」
au Starlink Directの仕組みは? ―スマホが直接衛星とつながり、100%のカバレッジ実現―
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/fujioka/2010587.html