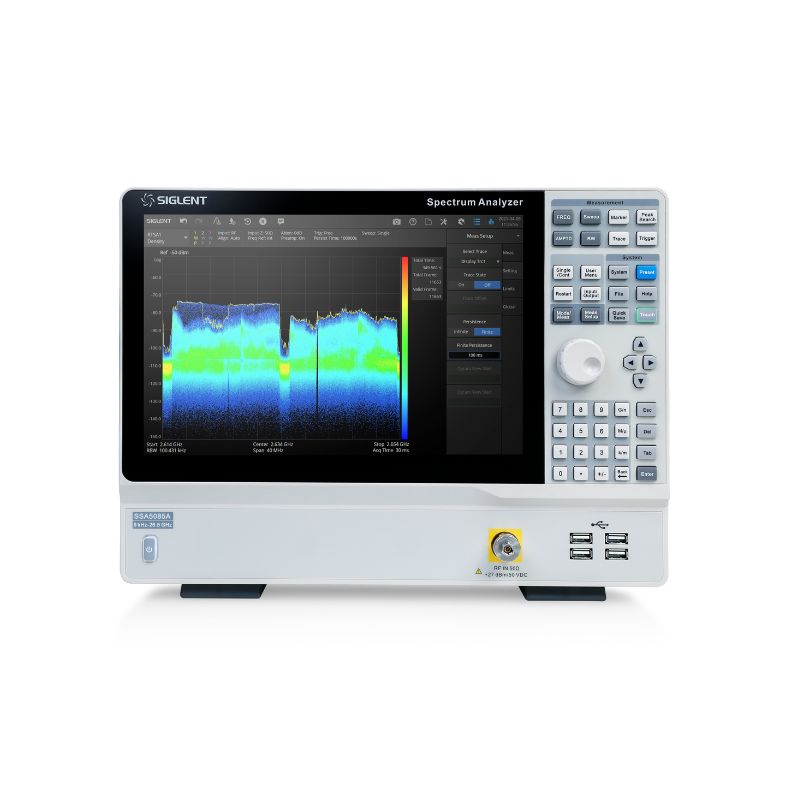携帯電話の周波数帯域は、1GHz以下のサブギガ帯(プラチナバンドなど)の他に、主に中周波数帯と高周波数帯があり、それぞれ異なる特性と利用目的を持っています。
以下に、携帯電話の主要な周波数帯域ごとの特徴をまとめます。
💻 携帯周波数帯域の分類と特徴
1. サブギガ帯(低周波数帯:〜1GHz)
-
周波数帯例: 700MHz、800MHz、900MHz帯(日本のプラチナバンド)
-
特徴:
-
広範囲カバレッジ: 電波が遠くまで届き、広いエリアをカバーできます(セル半径大)。
-
高い浸透性・回折性: 建物内や地下、山間部など障害物があっても電波が届きやすいです。
-
用途: 全国的なエリアの基盤、安定した通話・データ通信、エリアの穴埋めに必須。
-
デメリット: 帯域幅が狭いため、一度に送れるデータ量(通信速度)は高周波数帯に比べて控えめです。
-
2. 中周波数帯(ミッドバンド:1GHz〜6GHz未満)
この帯域は、4G LTEの主要帯域であり、5Gでは**Sub6(サブシックス)**と呼ばれ、高速化とエリアカバーの両立に重要な役割を果たしています。
-
周波数帯例: 1.5GHz、1.7GHz、2.0GHz、2.5GHz、3.7GHz、4.5GHz帯(5GのSub6)
-
特徴:
-
バランスの良さ: サブギガ帯よりは速度が出やすく、高周波数帯よりはエリアが広がりやすい、速度とエリアのバランスが良い帯域です。
-
大容量通信: サブギガ帯よりも広い帯域幅を確保しやすいため、都市部の高速通信や、トラフィック(通信量)が多い場所での利用に適しています。
-
用途: 4G LTEの主要な通信、5Gの基幹エリア展開の中心。
-
デメリット: サブギガ帯に比べると浸透性はやや劣るため、ビルが密集した場所では基地局を多く設置する必要があります。
-
3. 高周波数帯(ハイバンド:6GHz以上)
5Gで新たに活用が始まった帯域で、特に20GHz台後半は**ミリ波(mmWave)**と呼ばれます。
-
周波数帯例: 28GHz帯(5Gのミリ波)
-
特徴:
-
超高速・大容量: 非常に広い帯域幅(数百MHz)が確保できるため、5Gが実現する超高速通信(ギガビット級)を可能にします。
-
用途: スタジアム、駅、繁華街など、特定のエリアで超高速・大容量の通信が必要なホットスポット的な利用。
-
デメリット:
-
減衰が大きい: 電波が遠くまで届かず、基地局のカバー範囲が非常に狭いです。
-
障害物に弱い: 建物や壁、さらには雨や人の体にも遮られやすく、通信が途切れやすいという弱点があります。
-
-
🔄 世代と技術による使い分け
携帯キャリアは、これら異なる特性を持つ周波数帯域を組み合わせることで、全国的なカバレッジと、都市部での高速・大容量通信の両立を実現しています。
| 世代/技術 | 主な利用周波数帯 | 特徴 |
| 3G/4G (LTE) | 700MHz〜2.1GHz帯が中心 | 全国的な基本エリアと、都市部の容量確保を目的とする。 |
| 5G Sub6 | 3.7GHz、4.5GHz帯 | 4Gより速く、広いエリアを比較的迅速に展開するための主軸。 |
| 5G ミリ波 | 28GHz帯 | 5Gの真の高速性能を実現するが、エリアは非常に限定的。 |
特に5Gでは、異なる周波数帯を組み合わせて通信速度を高速化する**キャリアアグリゲーション(CA)**といった技術も活用されています。