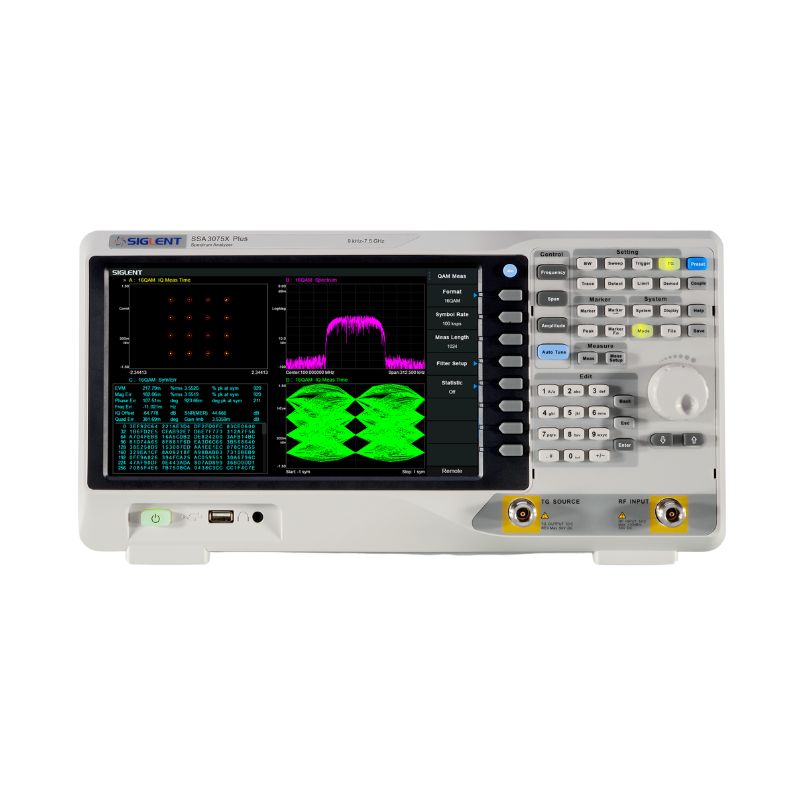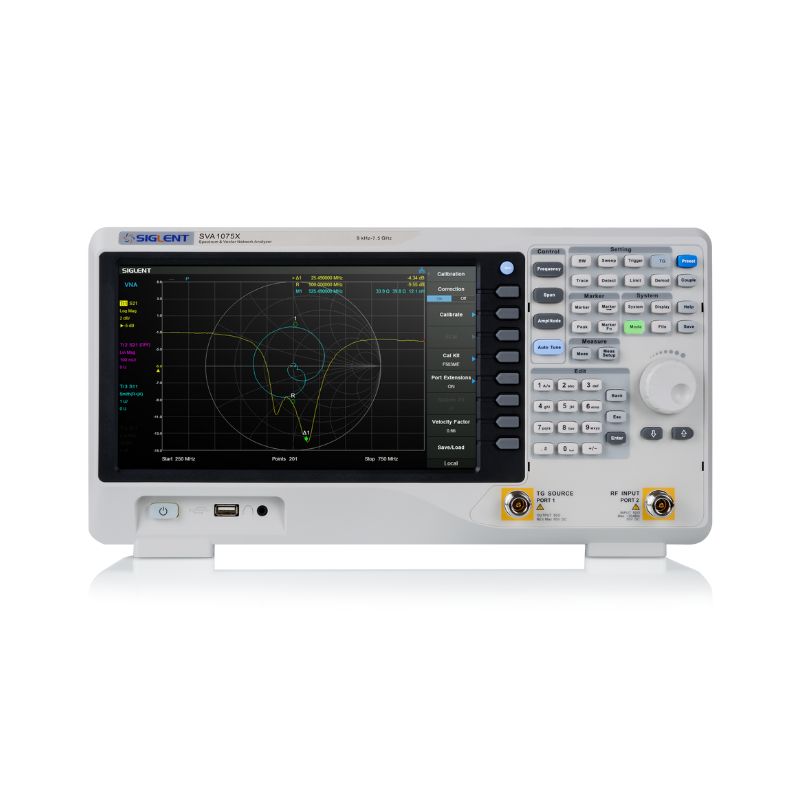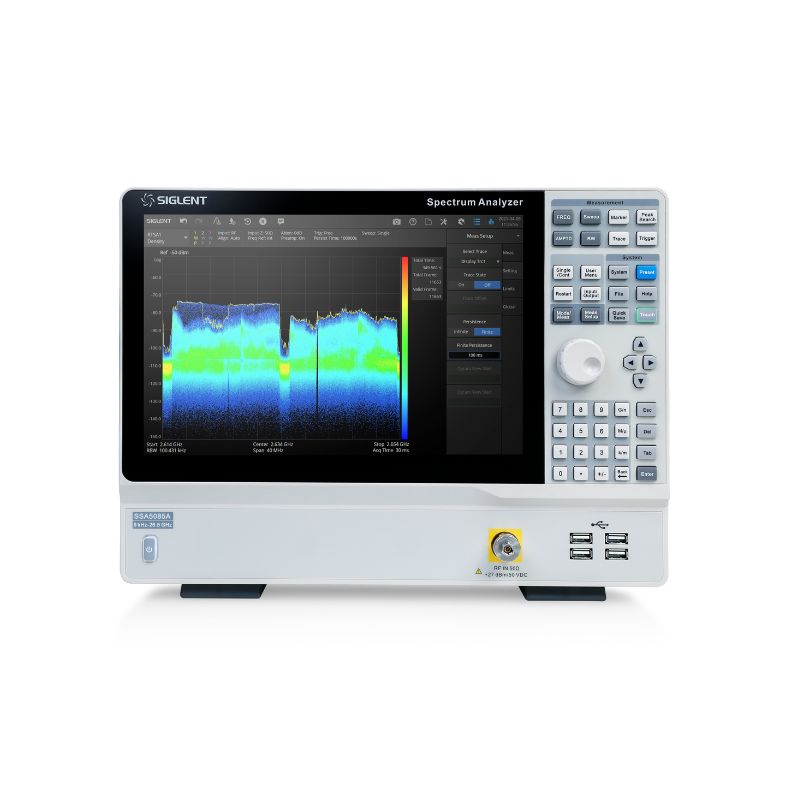水中無線通信技術は、水中ドローン(AUV/ROV)を活用した海底資源探査にとって不可欠な要素技術であり、その進展が調査の効率化と高度化を牽引しています。
水中無線通信技術の主要な方式
水中では電波の減衰が激しいため、陸上のような高速な無線通信が難しく、主に以下の技術が利用・研究されています。
-
水中音響通信(Acoustic Communication)
-
特徴: 音波(音響)を利用し、水中での伝搬性に優れ、数kmに及ぶ長距離通信が可能です。
-
課題: 伝搬速度が遅いため(水中での音速は約1,500m/秒)、通信速度が低速で、大容量データのリアルタイム伝送が困難です。また、海底や海面からの反射波(マルチパス)や海洋生物のノイズの影響を受けやすいです。
-
現状: 信号処理技術により通信の安定性・品質改善が進み、海中音響通信による完全遠隔無線制御型水中ドローンなども実現されています。
-
-
水中光無線通信(Underwater Optical Wireless Communication: UOWC)
-
特徴: 主に可視光(青色や緑色のレーザー光)を利用し、高速・大容量通信が可能です(Gbps級の通信が実証されています)。
-
課題: 海水中の濁りや粒子による減衰が大きいため、通信距離が短い(通常、数メートルから数十メートル、長くても100m程度が限界)です。また、通信を行うための厳密な光軸合わせが必要で、移動体間での通信や光軸追尾技術の開発が重要です。
-
-
水中電波通信(Radio Frequency: RF Communication)
-
特徴: 電波(特に低周波数帯域)を利用します。
-
課題: 水中での減衰が極めて大きく、数メートル程度の短距離しか通信できません。長距離化や高速化は困難です。
-
現状: 短距離であれば高データレートが可能であり、音響通信や光通信を補完する技術としての利用が検討されています。
-
水中ドローンと海底資源探査への応用
水中無線通信技術は、**AUV(自律型無人潜水機)やROV(遠隔操縦型水中ロボット)**といった水中ドローンによる海底資源探査の効率化と無人化に貢献しています。
探査システムにおける役割
-
広域探査の効率化: 複数のAUVをオペレーターが音響通信を介して群制御(スウォーム制御)することで、広範囲の海底を短期間で効率よく調査できます。
-
リアルタイム制御とデータ取得: AUV/ROVは、搭載されたソナー(SSSなど)やセンサー(磁気センサー、CTDセンサーなど)を用いて海底地形、熱水噴出孔、鉱物資源の反応などを探査します。
-
長距離探査には音響通信で遠隔操作や基本的な命令を伝達します。
-
至近距離での詳細なデータ転送や映像伝送には、光無線通信を利用して高速に大容量データを取得する応用が期待されています。
-
-
自律航行の高度化: GPSが届かない海中では、音響通信による測位システム(USBLなど)が水中ドローンの正確な位置制御と自律航行に不可欠です。
海底資源探査の具体例
-
海底熱水鉱床・コバルトリッチクラスト: AUVがプログラムされたルートを自律航行し、海底付近の詳細な地形データや水質・温度などの環境データを取得します。
-
マンガン団塊: 複数のAUVが協調して広範囲をスキャンし、磁気センサーや3D画像マッピングシステムと連携することで、「どこに」「どのような」資源があるかを高精度に特定します。
水中ドローンの技術進化(AI連携による画像解析、自律航行技術の高度化、LiDAR搭載による高精細計測など)と水中無線通信の高速化・長距離化が結びつくことで、海底資源探査は今後もさらに進展すると期待されています。