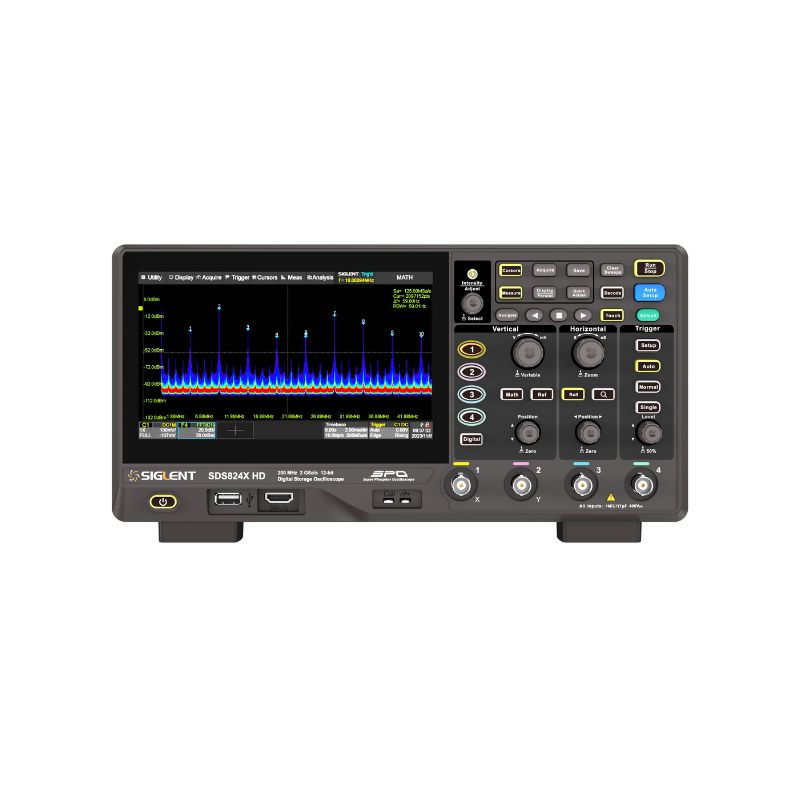二相変調法 (Two-Phase Modulation, TPM) とは
モーター駆動において、インバーターが出力する交流電圧波形を生成する方法の一つです。一般的な三相正弦波PWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation, SPWM)が、常に3つの相(U, V, W)すべてにスイッチングを行うのに対し、二相変調法は、常に2つの相のみをスイッチングし、残りの1つの相のスイッチングを停止します。これにより、スイッチング回数を減らし、スイッチング損失を低減できるという利点があります。
不連続点と電磁音・損失
二相変調法には、スイッチングパターンが切り替わる不連続点が存在します。この不連続点は、モーターに印加される電圧の不連続な変化を引き起こし、これが問題の原因となります。
-
電磁音の発生: 電圧の急激な変化は、モーターのトルク脈動や磁束の不連続な変化を引き起こし、これがモーターの振動や騒音(電磁音)の原因となります。特定の回転数や負荷条件でこの不連続点とモーターの固有振動が共振すると、特に大きな騒音が発生することがあります。
-
スイッチング損失: 不連続点そのものは、スイッチング損失に直接関係するものではありません。しかし、二相変調法では、スイッチングを停止する相を切り替える際に、急激な電圧の変化が生じます。この切り替えによって、各相の電圧が不連続になり、高調波電流が増加します。この高調波電流が、モーターの鉄損や銅損を増加させる可能性があります。
不連続点を考慮した二相変調法の改善
不連続点による電磁音と損失を両立させるためには、以下の様なアプローチが考えられます。
1. スイッチングパターンの最適化
不連続点の影響を低減するために、スイッチングパターンを最適化する手法があります。
-
電圧ベクトル切り替え点の平滑化: 従来の二相変調法では、電圧ベクトルの切り替えが瞬間的に行われますが、これを滑らかにすることで、電圧の変化を緩やかにし、電磁音の発生を抑えることができます。
-
不連続点の移動: 不連続点をモーターの回転速度や負荷に応じて移動させることで、特定の運転領域での共振や騒音のピークを避けることができます。
2. ハイブリッド変調法
二相変調法と三相変調法を組み合わせることで、それぞれの利点を活かす手法です。
-
低速域: 損失が支配的になる低速域では、スイッチング回数の少ない二相変調法を使い、効率を向上させます。
-
高速域: 電磁音が問題になりやすい高速域では、電圧波形が滑らかな三相変調法に切り替えることで、騒音を低減します。
3. 不連続点を活用した手法
不連続点をなくすのではなく、逆に活用して損失を低減する研究も行われています。
-
デッドタイム補償の最適化: スイッチングの不連続点を利用して、デッドタイム(IGBTなどのスイッチング素子が両方ONにならないように設ける時間)による電圧誤差を効果的に補償し、損失を低減させる手法などがあります。
これらの手法は、モーターの用途や要求される性能(効率、静粛性、コストなど)に応じて、最適なバランスを見つけることが重要です。
参考:日経クロステック
東京工業高等専門学校・綾野秀樹氏の研究グループ
二相変調法の不連続点に着目、モーター電磁音と損失低減を両立
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ne/18/00007/00267/?P=2
 |
出典: 東京工業高等専門学校・綾野秀樹氏の研究グループ |