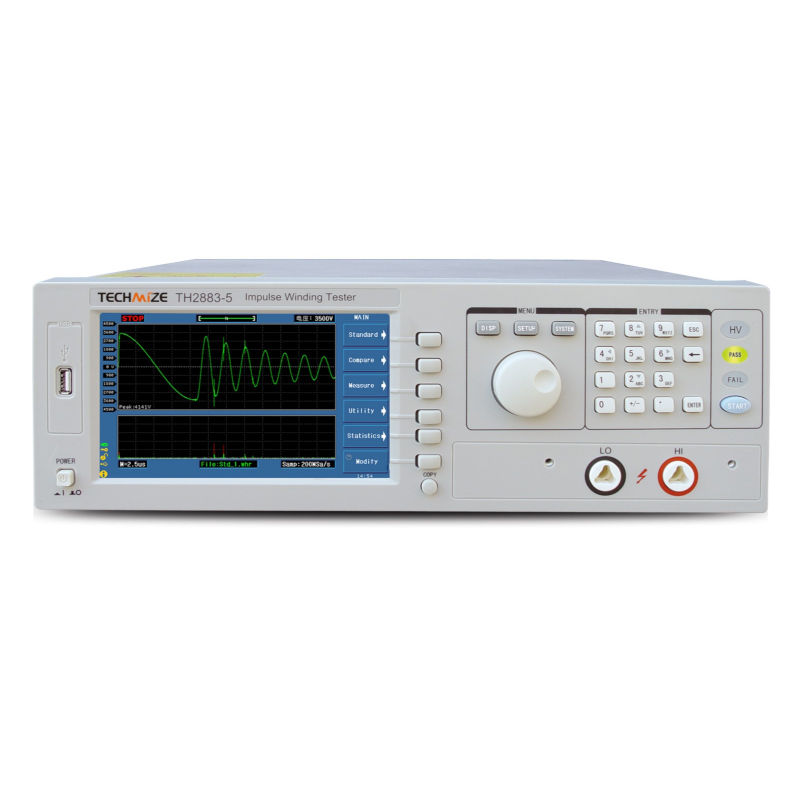― 基本操作、測定モード別活用法、標準波形の取得手順 ―
この章では、TH2883Sシリーズのユーザー操作手順、測定フロー、標準波形の取得方法、および測定対象に応じた設定の実用例について詳しく解説します。新規ユーザーの教育用資料としても有効です。
1. 基本操作と画面遷移
1.1 キーとローラーの使用方法
-
ローラー:上下回転で項目選択/押し込みで決定
-
[DISP]/[SETUP]/[SYSTEM]キー:メインメニュー切替
-
数字キー/矢印キー:数値入力またはカーソル移動
-
ESC/BACKSPACE/ENTER:入力の取り消し/修正/確定
1.2 画面遷移の基本構造
[DISP] → 測定表示画面(波形・比較)
[SETUP] → 測定条件、ステップ、ファイル管理
[SYSTEM] → 環境設定、I/O、言語、パスワード
2. 測定の基本フロー
2.1 非標準測定(Non-standard Test)
-
比較対象(標準波形)を持たない測定
-
波形観察や試験条件の最適化時に使用
2.2 標準波形との比較試験(Sample Test)
-
あらかじめ取得・登録された標準波形と比較し、自動でPASS/FAILを判定
-
量産ラインや良品検証用に最適
3. BDV(Breakdown Voltage)試験
-
目的:ターン間絶縁がどの電圧で破壊されるかを確認
-
特徴:設定された電圧範囲(Start Volt~End Volt)をVolt Stepの単位で増加させてテスト
-
自動停止:FAILが発生した時点で試験中止
4. 標準波形の取得と活用
4.1 Match Setupの活用
[SETUP] → Match Setupにて、以下の方法で標準波形を取得します。
| モード | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| Manual | 手動で波形を取得し平均化 | ユーザー主導、精密設定向け |
| Auto | 周波数を変化させながら自動収集 | 作業効率重視、初心者向け |
| Loop | 周回サンプリングと自動最適化 | 標準波形の安定収集に最適 |
4.2 Manualモード操作例
-
試験ステップを選択
-
Startを押して波形収集開始 -
Completeで収集完了 -
Averageで複数回平均化 -
UndoまたはUndo Allで修正可能
4.3 Autoモード操作例
-
Startで自動的に波形を収集 -
→/←で異なる周波数波形を選択 -
Selectで登録、またはSelect & Checkで比較検証後登録
5. 比較モードの使い分け
| 比較モード | 推奨対象 | 備考 |
|---|---|---|
| Area Size | 内部短絡検出 | 波形全体の面積差で評価 |
| Diff Area | 巻数/材質差検出 | 波形形状の差を評価 |
| Corona | 微小放電・絶縁劣化検出 | 高電圧印加時の高周波ノイズ検出 |
| Phase Diff | 構造的不均衡検出 | 波形のゼロクロスポイントを比較 |
6. 標準波形の再利用(SW.Copy/TW.Copy)
-
SW.Copy:他ステップの標準波形をコピーして利用
-
TW.Copy:直前の標準波形と比較を行う設定
例:ステップ01で収集した波形をステップ02にも適用
7. ファイル名と保存ルール
-
ファイル名は最大32文字、A-Z/0-9/アンダーバー使用可
-
標準波形の命名例:
TRANS_STD01、BDV_COREA_05など -
無入力の場合は
<Unnamed>が自動付与
まとめ
本章で紹介した一連の操作により、TH2883シリーズの測定・比較・標準波形取得の基本が理解できます。特にMatch Setup機能と各比較モードを理解することで、試験対象に合わせた柔軟な測定体制が構築可能です。
インパルス巻線試験器の入門①- 試験原理・構成・基本仕様の理解
インパルス巻線試験器の入門②-主要仕様と波形比較手法の解説
インパルス巻線試験器の入門③-測定表示とディスプレイ機能
インパルス巻線試験器の入門④-比較方式と判定アルゴリズム
インパルス巻線試験器の入門⑤-測定設定と試験ステップの構成(SETUP)
インパルス巻線試験器の入門⑥-システム設定と通信インターフェースの管理
インパルス巻線試験器の入門⑦-操作手順と標準波形の作成
インパルス巻線試験器の入門⑧-リモート制御用コマンドとSCPI準拠インターフェース
インパルス巻線試験器の入門⑨-ファイル管理とUSB/内部メモリ活用法
インパルス巻線試験器の入門⑩-インパルス試験の応用と実践的トラブル対応例