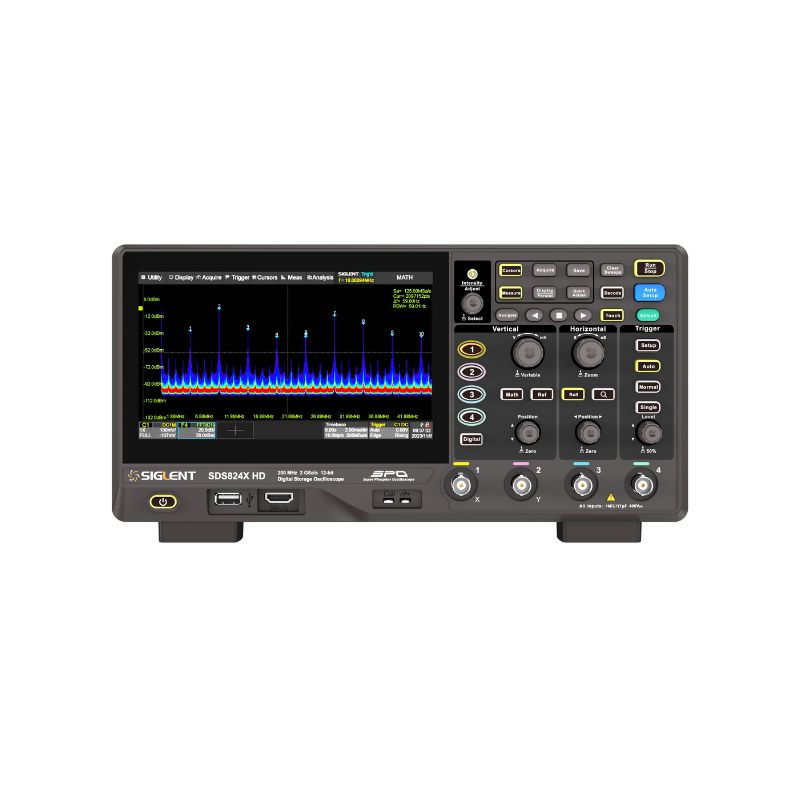SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)は、従来のSi(シリコン)よりも優れた特性を持つ**ワイドバンドギャップ半導体**ですが、その優れた物性ゆえに、ウェハの加工技術にはSiチップ製造とは全く異なる難しさがあります。
ここでは、SiCやGaNウェハの加工技術の特徴と、それに伴う課題を解説します。
1. 結晶成長・基板作製プロセス
ロジックチップではSi単結晶を溶融凝固させてインゴットを作るのに対し、SiCとGaNではそれぞれ特有の困難なプロセスを用います。
-
SiC(昇華法が主流):
-
超高温プロセス: 結晶成長に約 2000°C を超える超高温が必要であり、成長速度が遅いのが課題です。
-
高硬度:SiCはダイヤモンドに次ぐ硬度を持つため、インゴットからウェハを切り出すスライスや、表面を平坦にする**研削・研磨(CMP)**に非常に時間がかかり、コスト高の最大の要因の一つとなっています。
-
-
GaN(サファイア/Si上エピタキシャル成長が多い):
-
高品質基板の難しさ: GaNはSiCに比べて、結晶成長が難しく、高品質なGaN単独基板(ホモエピタキシャル)の製造が難しいため、現在でもサファイアやSiC、またはSi基板の上に薄膜を成長させるヘテロエピタキシャル成長が主流です。
-
欠陥制御: 特にSi基板上にGaNを成長させる場合、格子定数の不一致により**欠陥(ディスロケーション)**が発生しやすく、デバイスの信頼性を高めるための欠陥制御技術が重要になります。
-
2. デバイス形成プロセス(微細加工)
ウェハ上にトランジスタ構造を形成するプロセスにおいても、従来のSiとは異なる技術が必要です。
🛡️ エッチングの難しさ
-
高耐食性: SiCやGaNは化学的・熱的に非常に安定しているため、Siで一般的に使われるウェットエッチング(薬品による溶解)がほとんど使えません。
-
ドライエッチングの採用: 構造形成のためには、プラズマを使ったドライエッチング が必須となりますが、このプロセスでもSiよりも時間がかかり、加工面の損傷(ダメージ)を最小限に抑える技術が求められます。
🔥 オーミックコンタクト形成(低抵抗接続)
-
超高温アニール: SiCやGaNに電極(金属)を形成する際、電流をスムーズに流すための低抵抗な接続(オーミックコンタクト)を得るために、1000℃近い超高温での熱処理(アニール)が必要です。
-
金属の選定: 使用する金属(Ti/Alなど)やアニール条件の最適化が、デバイスの性能と信頼性を決定する重要な鍵となります。
3. 裏面プロセス(垂直構造の実現)
パワーデバイスの多くは、大電流を流すための垂直構造 を採用するため、裏面加工技術が極めて重要です。
-
ウェハの薄化と裏面研削:
-
高耐圧層を確保しつつ、デバイス動作時の熱抵抗を低減し、かつダイシング(チップ分割)をしやすくするために、ウェハを最終的に数十μm程度まで薄くする**裏面研削(バックグラインディング)**を行います。
-
高硬度のSiCでは、ウェハを割らずに薄く加工する技術(エッジ部の補強や研磨技術)が特に重要です。
-
-
裏面電極形成:
-
ウェハの裏面全体に、大電流を取り出すための厚い金属電極を形成します。これは論理チップの表面配線とは目的が全く異なります。
-
これらの特殊な加工技術の確立と、ウェハの大口径化(4インチから6インチ、さらに8インチへ)および高品質化が、SiCやGaNデバイスのコストダウンと普及に向けた最大の課題となっています。