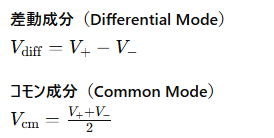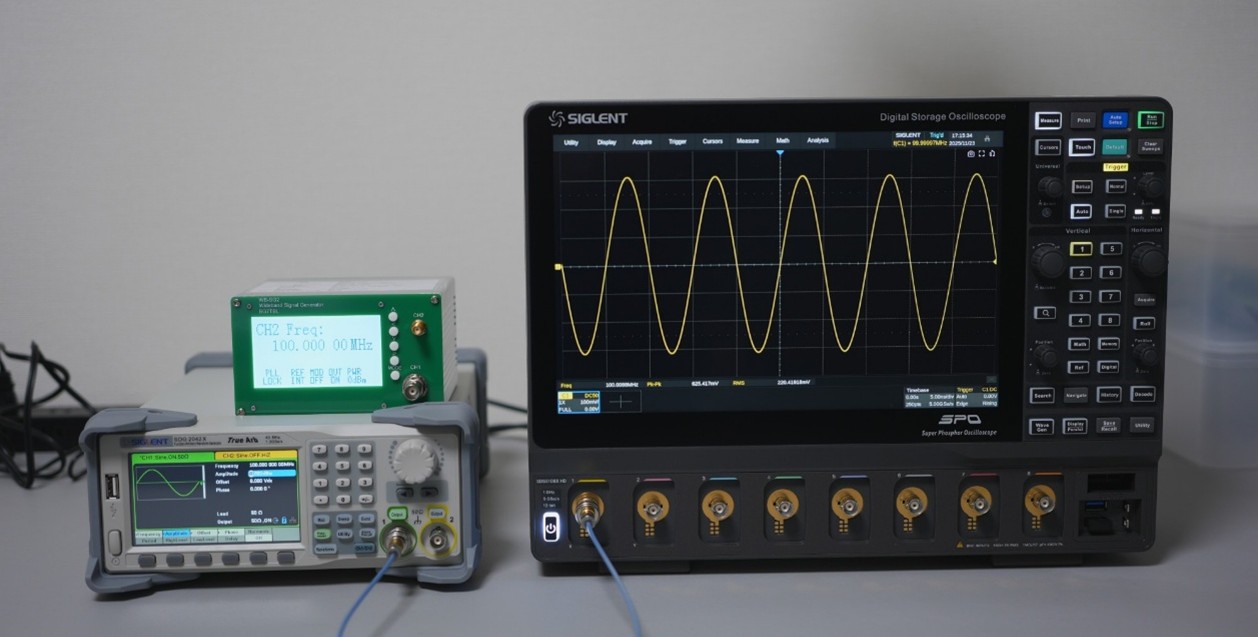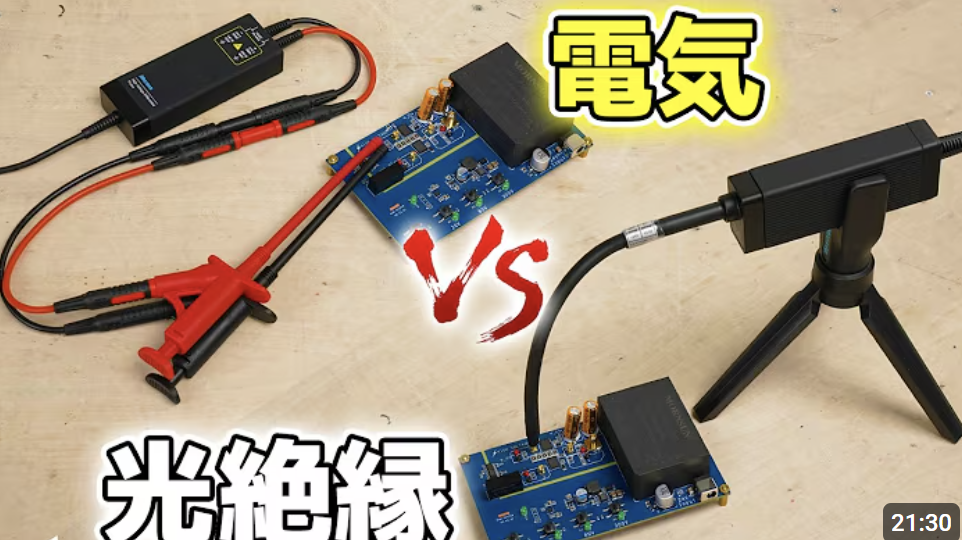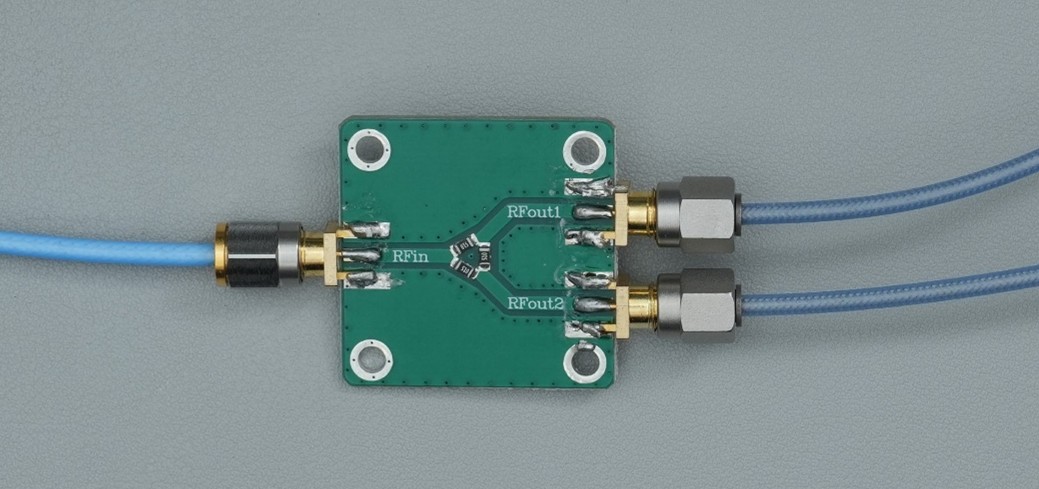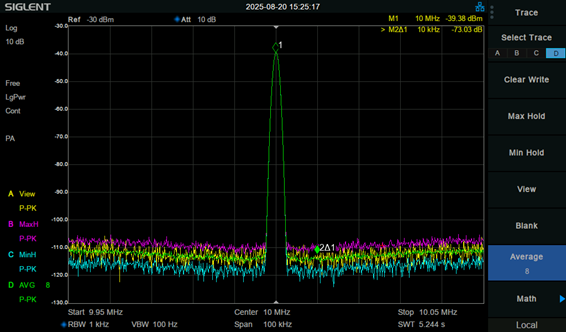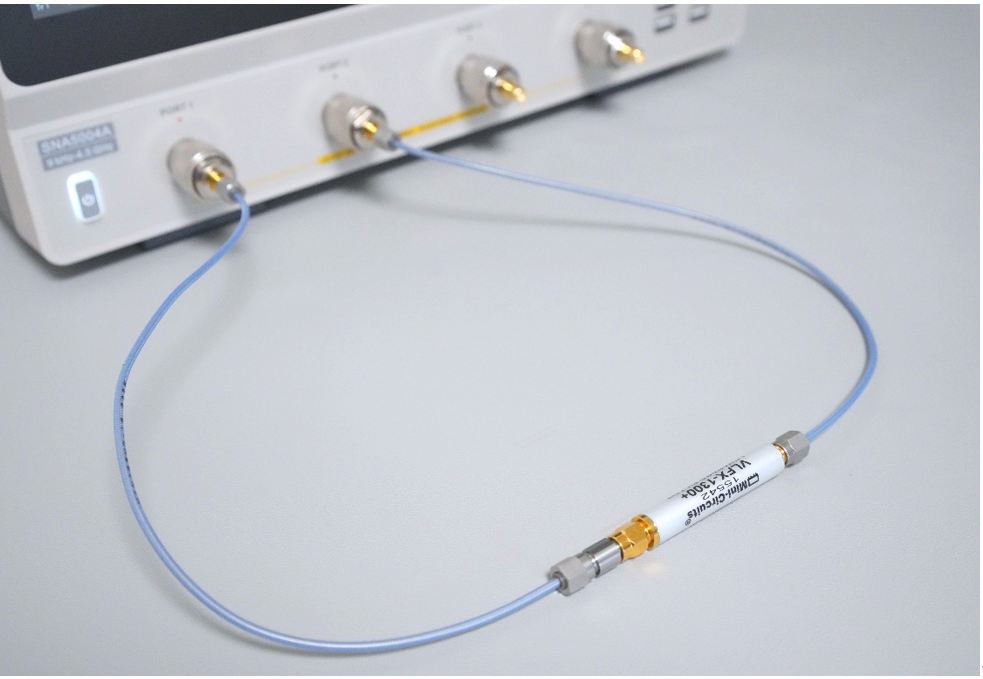電子計測や信号伝送、電源回路、さらには高周波設計やEMC対策において、「コモン電圧(Common Voltage、共通モード電圧)」という概念は非常に重要な役割を担っている。差動信号や電源ラインに潜むコモン電圧は、測定精度の低下、誤動作、ノイズ放射、絶縁破壊といった重大な問題を引き起こす可能性がある。しかし、実務現場では「差動測定 = メイン」と考えられることが多く、コモン電圧の扱いが軽視される傾向がある。本稿では、コモン電圧の定義から発生メカニズム、影響、測定方法、対策まで体系的に整理し、その重要性を多角的に解説する。
1. コモン電圧とは何か
コモン電圧とは、「基準点(通常はGND)に対して、信号ラインが共通して持つ電圧成分」のことである。
差動信号では次式で表される:
理想的な差動信号ではコモン電圧はゼロに近いことが望ましいが、ドライバの偏差、負荷の不均衡、配線の非対称性、外来ノイズなどによって実際には必ず発生する。
2. コモン電圧が生じる主な要因
コモン電圧の発生要因を理解することは、トラブルシュートと設計改善において極めて重要である。
2.1 ドライバICや回路素子の不均衡
-
トランジスタのばらつき
-
出力抵抗のズレ
-
電源電圧の変動
-
温度ドリフト
これらにより正負ラインが揃わず、コモンモード電圧が発生する。
2.2 PCBレイアウトの非対称
-
ペア配線の長さ不一致
-
結合差
-
GNDプレーンの欠け
-
ビア配置の左右差
差動バランスが崩れ、コモンモード成分が増加する。
2.3 外来ノイズの乗り込み
-
スイッチング電源ノイズ
-
EMI
-
クロストーク
これらは「両ラインに同相で乗る」ためコモン成分となる。
2.4 絶縁・フローティング環境
基準電位が揃わないため大きなコモン電圧が発生しやすい。
3. コモン電圧が及ぼす影響
軽視すると重大なトラブルを生む。
3.1 測定精度の低下
計測器・プローブには CMVR(Common Mode Voltage Range) が存在する。
-
入力が飽和する
-
波形が歪む
-
クリップが発生
-
最悪入力回路が破損
特にインバータやモータ駆動では顕著。
3.2 デジタル通信の誤動作
CAN、RS-485、LVDS などの差動通信はコモン電圧の影響を大きく受ける。
-
レシーバが追従できずエラー
-
ビットエラー率上昇
-
通信断
規格が最大コモンモード電圧を定めるのはそのためである。
3.3 EMCノイズの増加
差動ラインは誤解されがちだが、コモン成分が増えると 強力なアンテナ となりノイズが放射される。
3.4 GNDループによるトラブル
工場設備などでは GND電位差が大きく、これがそのままコモン電圧となり、
-
過電流
-
絶縁破壊
-
機器の誤動作
を引き起こす。
4. コモン電圧の測定方法と注意点
正確な測定にはいくつかのポイントがある。
4.1 オシロスコープ + 差動プローブ
-
CMVR超過に注意
-
プローブ帯域は十分か
-
リード線の取り回しでノイズを拾いやすい
最近の高性能プローブ(MICSIG OPシリーズ、SIGLENT差動プローブなど)はCMRR・CMVRが高く実用的。
4.2 アイソレーションアンプ
フローティング測定に向くが、帯域や飽和に注意。
4.3 スペクトラムアナライザ+電流プローブ
コモンモードノイズの周波数特性解析に有効。
5. コモン電圧を抑制する設計上のポイント
5.1 発生源対策
-
ドライバの対称性確保
-
電源ノイズ低減
-
GNDインピーダンスの低減
-
出力抵抗のマッチング
5.2 配線レイアウト
-
差動ペアの等長化
-
GNDプレーンの連続性
-
ビア数・位置の左右対称化
-
ペアは常に近接・対称に配線
5.3 フィルタ・絶縁対策
-
コモンモードチョーク
-
EMIフィルタ
-
絶縁ドライバ
-
シールド
6. パワーエレクトロニクスでの重要性
MOSFET/IGBT を使うインバータでは特に問題が顕著。
-
高いスイッチング周波数
-
高 dv/dt
-
モータなど大容量負荷
-
広いGND構造
スイッチングノードの急峻な立ち上がり・立下りは浮遊容量を通じて他回路に伝搬し、誤動作やノイズを引き起こす。
7. まとめ
コモン電圧は“見えにくいが最も多くのトラブルを生む要因”である。
-
測定誤差
-
通信障害
-
EMC不適合
-
半導体破損
-
システムの誤動作
これらはコモン電圧を理解し、適切な対策を施すことで大きく改善できる。
差動信号、電源回路、パワエレ、産業機器、高周波回路など あらゆる分野で、コモン電圧の管理は信頼性向上の最重要項目である。
© 2025 T&Mコーポレーション株式会社