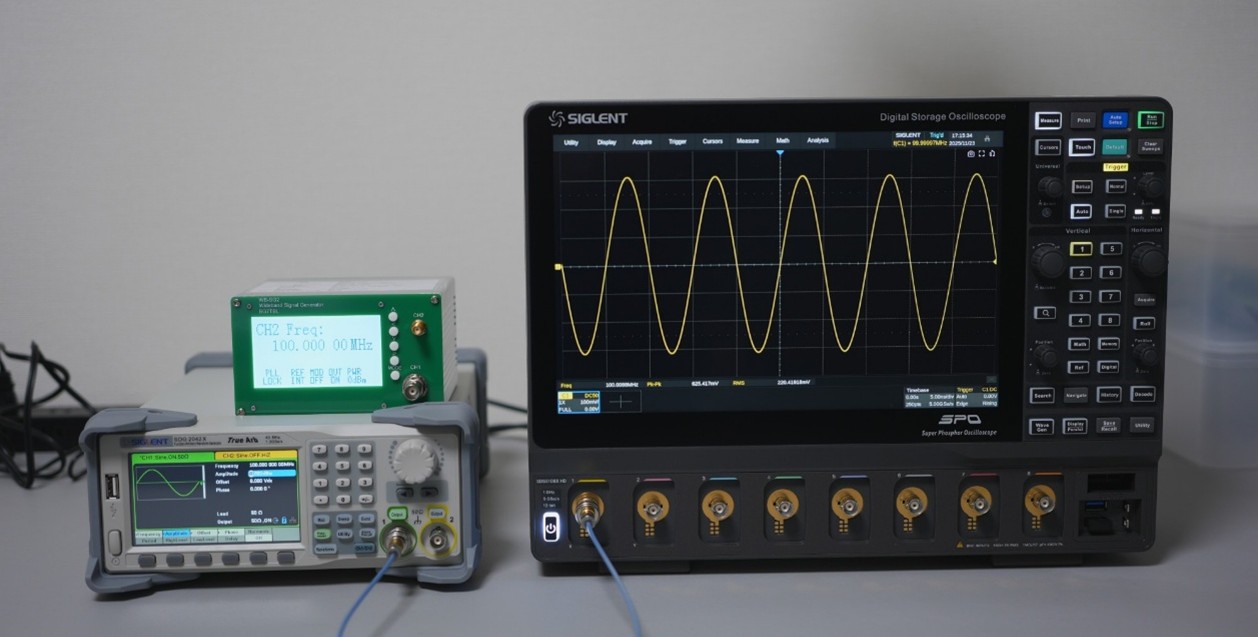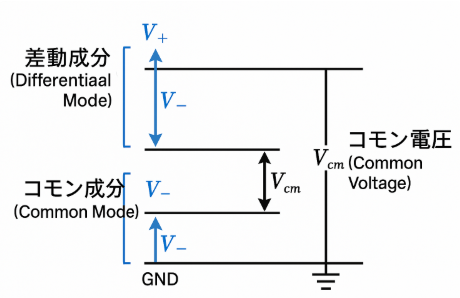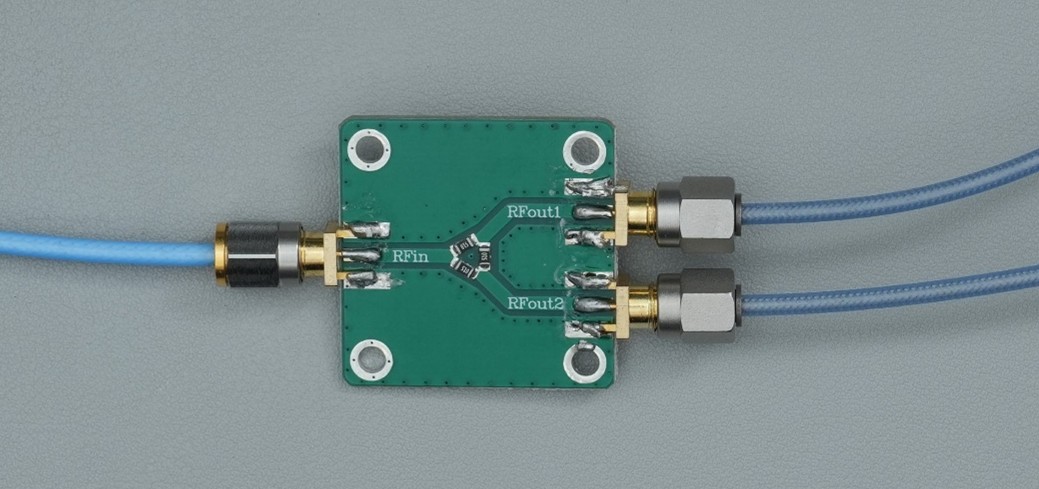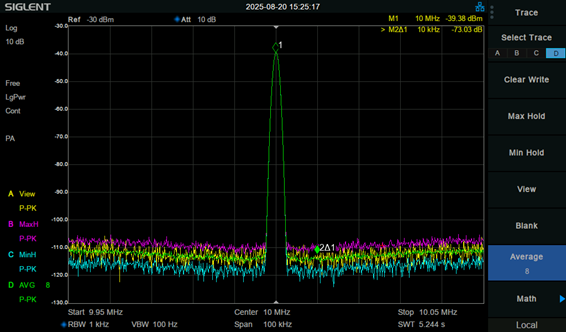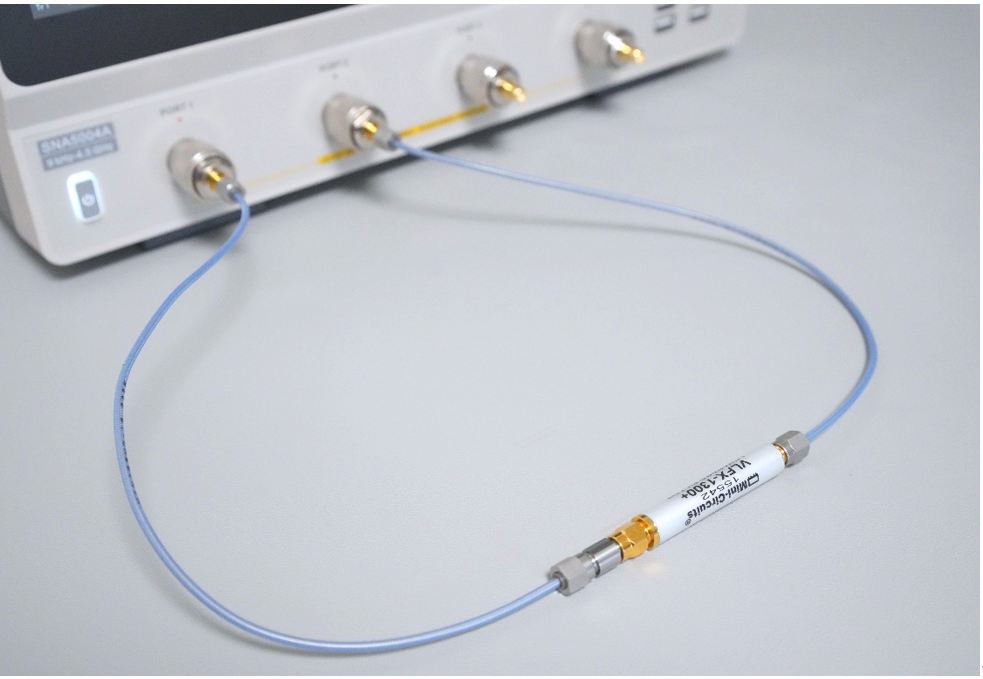オシロスコープで用いる 3 種類のプローブ(受動プローブ・高電圧差動プローブ・光絶縁プローブ)を比較し、を実験を通して分かりやすく解説しています。
• 測定方法の違い
• 波形に与える影響
• 高いコモンモード電圧条件での性能差
• パワーエレクトロニクス分野で光絶縁プローブが有利な理由
1. 受動プローブの制約
✔ 構造上の問題点
一般的な受動プローブは、グラウンドリードが全チャンネルで共通化(オシロ内部で接続)されています。
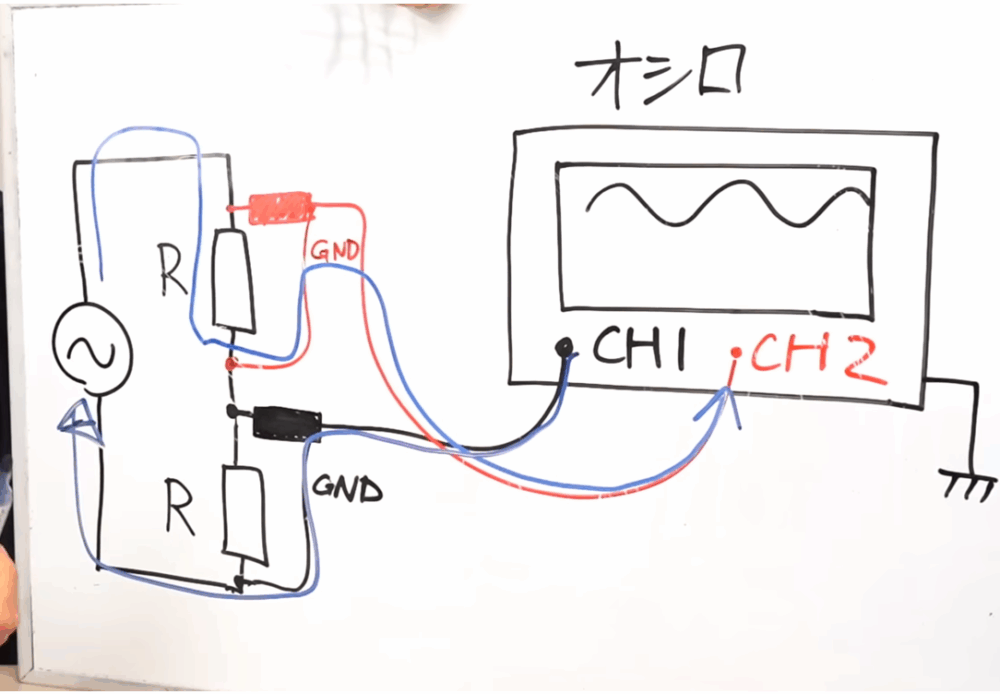 |
そのため:
• 2つの受動プローブで浮いたポイントを同時測定すると グラウンドループが発生
• 場合によっては大電流がオシロ内部に流れ、 プローブの GND リードが焼損する危険
• 波形が本来の値と全く異なる
✔ 浮遊(ふゆう)測定の代替方法
Math 機能で差分(V1−V2)を取ることで測定は可能だが、
• 測定したい信号が小さいと ノイズが極端に増える
• 高周波成分はほぼ正確に測れないという弱点があります。
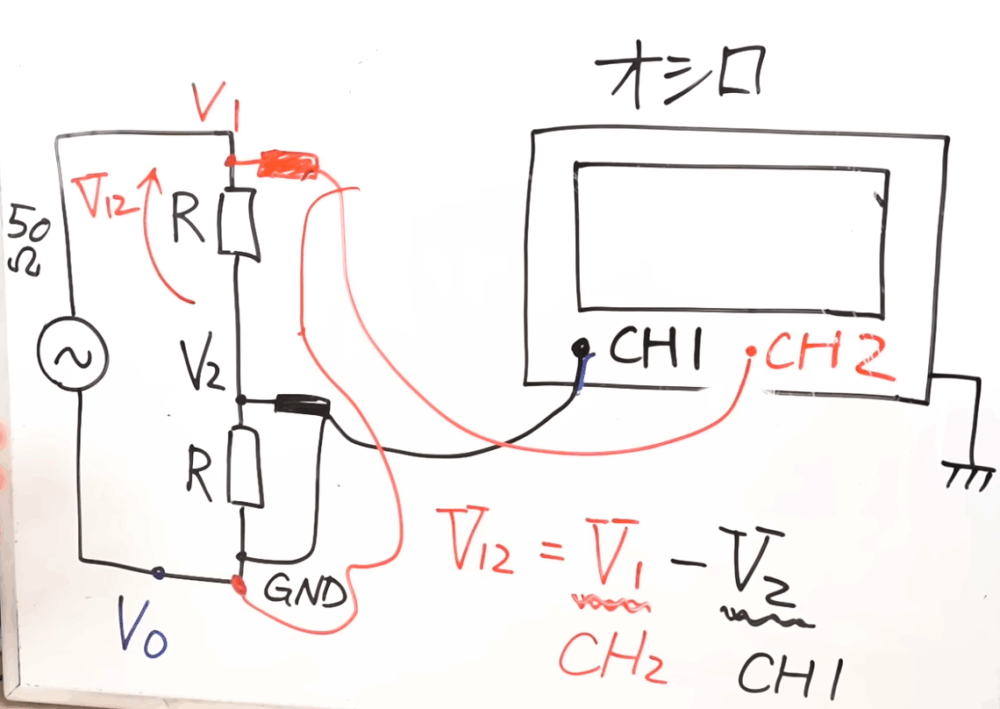 |
2. 高電圧差動プローブの特徴
✔ メリット
• 任意の 2 点間電圧を直接測定できる
• 電圧計のような感覚で使える
• 受動プローブより便利
✔ しかし限界もある
差動プローブの実際の動作原理は、
• A 点・B 点の電圧を オシロのグラウンド基準 でそれぞれ取得
• 内部で差分を演算して表示
となっています。
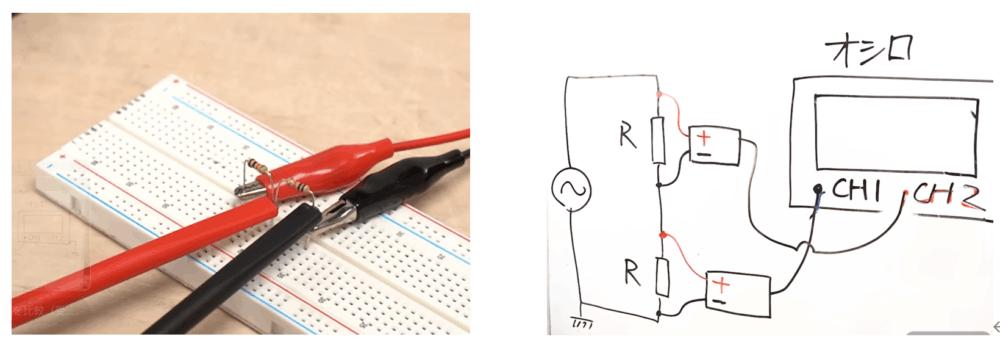 |
そのため:
• オシロと絶縁されていない
• コモンモード電圧の耐量は 2~3 kV 程度
• 高周波になるほど CMRR が悪化
• プローブ配線の取り回しで波形が大きく変わる → 再現性が低い
✔ 実験結果(高周波)
• 1 kHz:ほぼフラット
• 50 MHz:明確なコモンモードの影響やリンギングが発生
3. 光絶縁プローブ(Optical Isolation Probe)の構造と利点
✔ 構成(4 要素)
1. 測定チップ
2. 測定ヘッド
3. 光ファイバー
4. 受光部(BNC 接続)
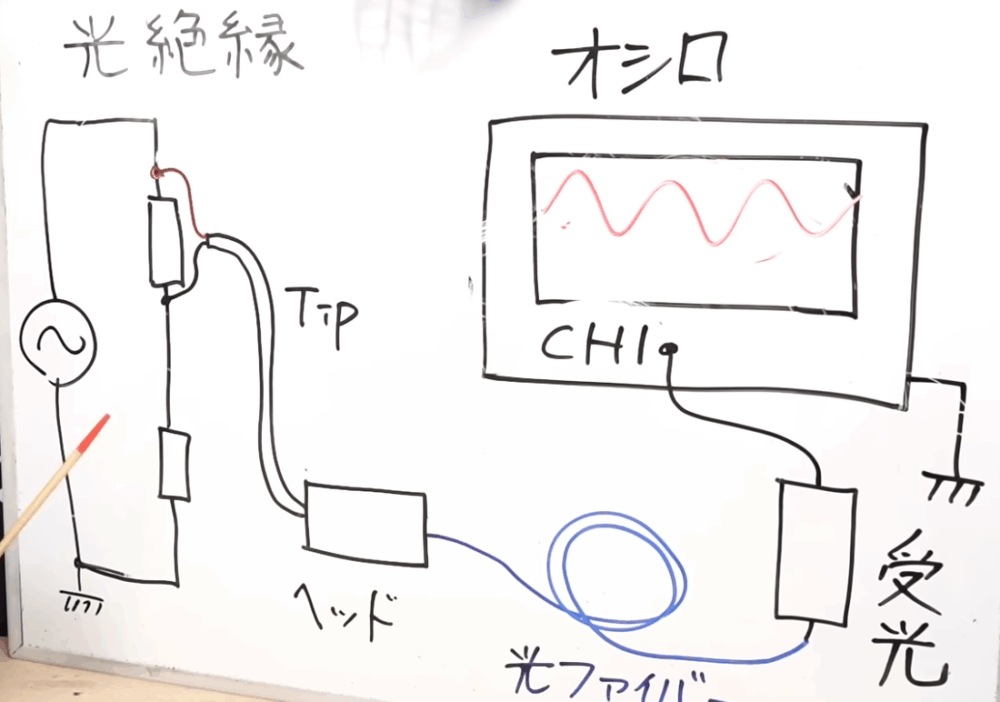 |
✔ 光絶縁プローブの主な強み
① 完全な電気的絶縁(トゥルー・フローティング)
• 測定基準は「被測定回路側」に存在
• コモンモード電圧は 50〜60 kV 程度まで対応
(差動プローブの 10〜20 倍以上)
② 極めて高い CMRR(同相信号除去比)
高周波のコモンモード成分にも強く、波形はほぼ 0V フラット を維持。
③ 測定の再現性が高い
• 配線取り回しによる影響がほぼない
• 技量に依存せず、誰が測っても同じ結果
④ 回路への負荷が非常に小さい
• パワエレ回路への影響がほぼゼロ
• 誤動作を引き起こしにくい
4. GaN 半橋回路での実測比較
✔ 測定対象:GaN ハーフブリッジの上側 Vgs
Source 端子が 0V〜300V を高速に行き来するため、
ここは 非常に高いコモンモード dv/dt ポイント。
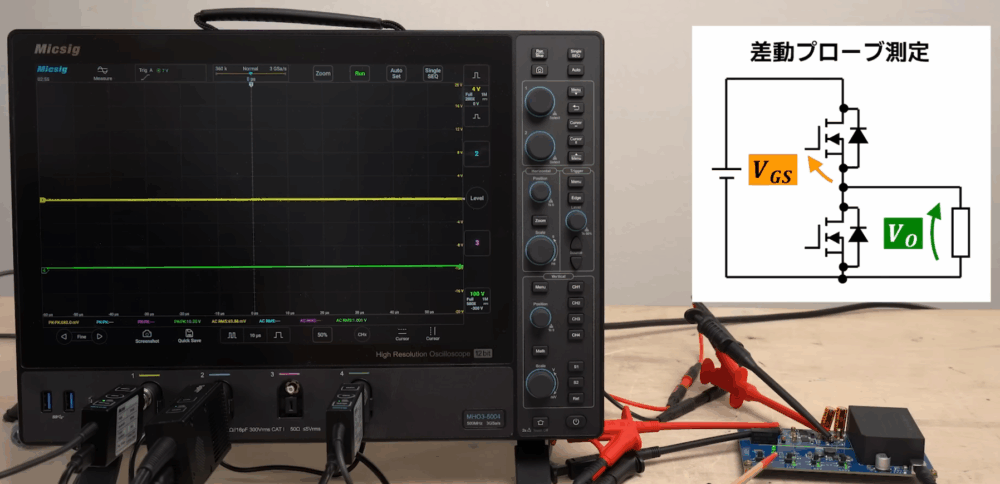 |
🔶 差動プローブの場合
出力電圧を 20V → 80V → 300V と上げると、
• 振動(リンギング)が急激に増加
• 300V 条件では 明らかな誤動作 が発生
o Vgs 波形が乱れる
o 回路が正しくスイッチングしない
差動プローブ自身が負荷となり、回路に悪影響を与えてしまう。
🔷 光絶縁プローブの場合
• リンギング無し、非常に綺麗な Vgs
• 300V 条件でも回路は安定動作
• 測定対象への負荷が極めて小さい
• “真の波形” により近い結果を取得可能
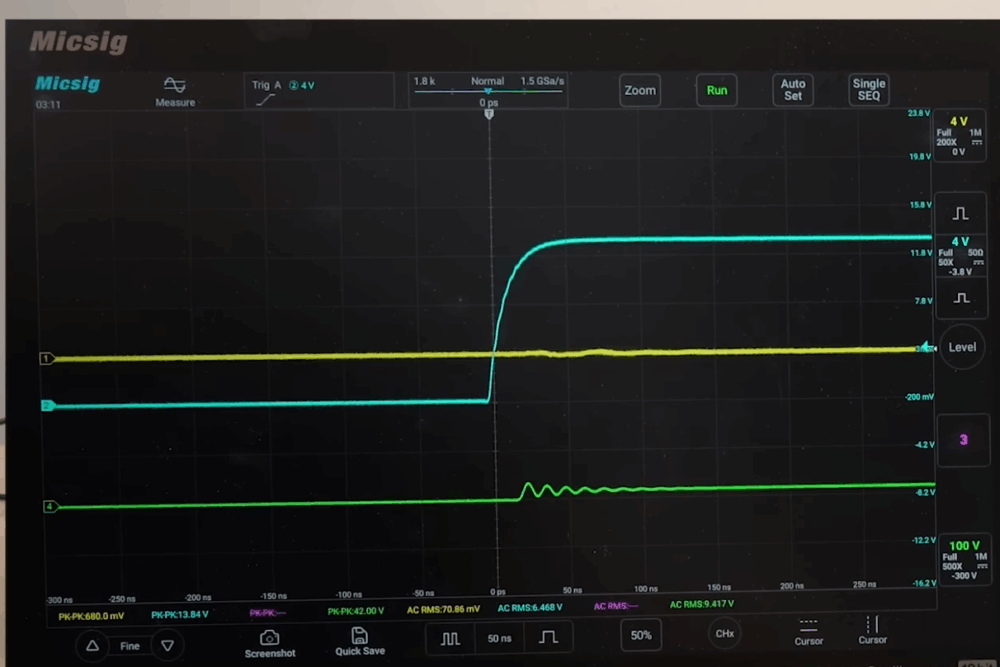 |
5. 総合まとめ
|
項目 |
受動プローブ |
差動プローブ |
光絶縁プローブ |
|
電気的絶縁 |
× |
× |
◎ 完全絶縁 |
|
浮遊測定 |
Math 必要 |
直接可能 |
直接可能 |
|
コモンモード耐量 |
極低 |
2〜3 kV |
50〜60 kV |
|
高周波 CMRR |
× |
△(技量依存) |
◎ 非常に高い |
|
再現性 |
低い |
中程度 |
高い |
|
測定対象への負荷 |
大 |
中 |
小 |
|
パワエレ用途 |
不適 |
場合により不安定 |
最適 |
© 2025 T&Mコーポレーション株式会社